
こんにちは🌿フクです。
本記事では【世代を超えて愛される絵本】をテーマに、
年間400冊以上の絵本を読み聞かせしている絵本大好きフクさんが、
おすすめの絵本を10冊選んで紹介しています。
小さなお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで世代を問わずにおすすめの絵本です。
世代を超えて愛される絵本とは
世代を超えて愛される絵本には、時代が変わっても多くの人々の心に響く普遍的な魅力があります。
そのような絵本には、いくつかの共通した特徴があるんです✨
シンプルで深いストーリー
名作絵本は、シンプルなストーリーの中に人生の大切な教訓や感動を込めています。
そして、子どもには理解しやすく、大人が読んでも深く考えさせられる内容が特徴です。
魅力的なイラストとデザイン
視覚的な美しさも長く愛される絵本の重要な要素です。
独特の色使いやタッチが印象的で、何度も見返したくなる絵本は記憶に残りやすいです。
普遍的なテーマ(愛、友情、勇気など)
時代を超えて読まれる絵本は、どの世代の読者にも共感できるテーマを持っています。
親子の愛、友情、挑戦する心、助け合うことの大切さなど、人生の根本的な価値を伝えてくれます。
懐かしい記憶と新たな気づき
親世代が子どもの頃に読んだことがある絵本は、幼い頃の記憶を重ねることができます。
まるで子供時代ののアルバムを見ているような懐かしい気持ちになれるのです。
そして、小さい頃には気づけなかった物語のコアの部分を知り、現在(いま)の自分に重ねて新しい発見をすることができます。
世代を超えて愛され続ける絵本たち
さっそく愛され続ける魅力的な絵本たちを見ていきましょう✨
ぐりとぐら なかがわりえこ、やまわきゆりこ(1963年)
「大きなたまご」で作るカステラのエピソードは、多くの方にとって忘れられない名場面ですよね。
フライパンいっぱいの大きなふんわりしたカステラ。
中川李枝子さんと山脇百合子さん姉妹による夢のような物語です。
『ぐりとぐら』は、その魅力的なストーリーやシンプルで可愛いイラスト以外にも、
リズム感のある言葉遣いも読者をとても楽しい気持ちにさせてくれますね。
ぐりぐらぐりぐら♪ぐりぐらぐりぐら♪
私事ですが、従兄弟の家で初めて『ぐりとぐら』の絵本を読んだ時、
「どうしてうちにこの絵本がないのか」そう思いました。
そして、従兄弟の家に行くたび、『ぐりとぐら』を読んでいたこと、
絵本からカステラの匂いがしたこと(実際は無臭です)、
従兄弟の家には大きなカステラがあるような錯覚すら抱いていた子供時代でした。笑
誰もが認める日本が誇るロングセラー絵本です!
スイミー レオ・レオニ(1963年)
絵本『スイミー』は「勇気」「協力」「個性」「知恵」「逆境からの立ち直り」など、
多面的なテーマを持つ物語です。
読み手によって感じ取るメッセージが異なるため、大人も子どももそれぞれ異なる視点で楽しむことができることが最大の魅力だと言えますね。
子供の頃『スイミー』を読んだ時、みんなで力を合わせて大きな魚に立ち向かうラストシーンで、そのアイデアに驚いたことと、『スイミー』に仲間ができた喜びで満たされた記憶があります。
『スイミー』は、「一人ではできないことも、みんなでなら可能になる」という希望と、「自分自身の特性を受け入れ、それを活かすことの大切さ」を教えてくれました。
国語の教科書で、『スイミー』のお話を知ったという方もいると思います。
絵本特有の質感で読むと一味も二味も違って感じることができるのでおすすめですよ✨
はらぺこあおむし エリック・カール(1969年)
絵本『はらぺこあおむし』は、カラフルな色と穴の空いた仕掛け絵本で、小さな子供たちの興味をひく要素がたっぷり詰まった作品です。
物語は「成長」「生命」「変化」という普遍的なテーマを扱っていて、小さなあおむしがどんどん成長していく喜びや、大人へと変化していくことの素晴らしさが伝わってきます。
月曜日、火曜日と曜日を覚えたり、登場する食べ物を暗記していたり、卵からあおむしが生まれ、やがて蛹になり蝶になることを学ぶ子供たちは多いのではないでしょうか。
『はらぺこあおむし』は、通常版だけでなく、ボードブック版、ミニ版、とびだす絵本版など、多様な形態で展開されており、用途や年齢に応じて選べる点も魅力ですね。
うちにはボードブック版があり、子供のやんちゃ時代の心強い相棒でした。
エリックカールによる美しいビジュアルとシンプルながら奥深いストーリーで、世界中の子どもたちとその家族から愛され続ける不朽の名作ですね。
ねずみくんのチョッキ なかえよしを(1974年)
「ねずみくんチョッキをきせてよ」「少しきついが似合うかな?」
ねずみくんの大切な赤いチョッキを、いろんな動物たちが「着てみたい!」と言って、次から次へとチョッキはどんどん大きな動物へと渡っていきますが、いろんな動物たちが小さなチョッキを無理やり着る姿がなんだかおかしくて、思わずクスッとしてしまいます。
でも、「大丈夫かな…?」と少しハラハラする気持ちも。
最後にチョッキを着たのは、大きなゾウさん。
チョッキは破れなかったけれど、びろ〜んと伸びてしまいました。
お母さんが編んでくれた大切なチョッキがこんなに伸びてしまって、ねずみくんはしょんぼり。
でも、最後のページをめくると、ゾウさんの鼻にぶら下がったチョッキをブランコにして、楽しそうに遊ぶネズミくんの姿が。
「貸してあげる」というねずみくんの優しさ、チョッキがどんどん伸びていく様子に感じるちょっぴり切ない気持ち、そして最後に見えるゾウさんの優しさ。
物語を読み終えたとき、子どもたちはほっと安心して、自然と笑顔になるのでしょう。
心地よいリズムの言葉と分かりやすい内容で、ハラハラしながらもラストはとっても優しい気持ちに✨
何世代にもわたって愛される絵本ですね。
100万回生きたねこ 佐野洋子(1977年)
絵本『100万回生きたねこ』は、「愛」「生と死」「幸せ」といった大切なテーマを優しく描いています。
主人公のねこは、何度も生まれ変わる中で、初めて誰かを愛し、愛されることの喜びや悲しみを知ります。その物語は、子どもだけでなく、大人の心にも深く響くものがあります。
最初のねこは、自分が一番大切で、他の存在に関心を持たずに生きていました。でも、白いねこと出会い、「誰かを愛すること」の意味を知ります。この変化を通して、読者は「本当の幸せとは何か?」と自然に考えさせられます。
また、この絵本には、輪廻転生や愛の本質についての深いメッセージが込められています。
読むたびに、新しい気づきがあるのも魅力のひとつです。特に、「愛すること」と「愛されること」の違いや、それがどのように幸せにつながるのかを、静かに問いかけてくれています。
物語の最後、白いねこの死を前にして、ねこは初めて100万回泣きます。
そして、今度は自らも静かに死んでいきました。もう二度と生き返らなかったのは、「本当の幸せ」を見つけたから──。そう解釈されることが多く、この結末が多くの読者の心に深く残ります。
子どもにとっては心に残る物語として、大人にとっては人生や愛について考えさせてくれる一冊。
世代を超えて愛され続ける、特別な絵本です。
ウォーリーをさがせ! マーティン・ハンドフォード(1987年)
探し絵本の元祖といえば、やっぱり『ウォーリーをさがせ!』
緻密に描かれたイラストは、見るたびに新しい発見があり、ユーモラスなシーンや予想外の出来事がページいっぱいに散りばめられています。
ウォーリーを探すだけでなく、その世界観自体を楽しめるのが魅力です。
『ウォーリーをさがせ!』は、家族みんなで楽しめるのはもちろん、「待ち時間対策の神アイテム」でもあります。病院の待合室や電車の中で、度々助けられました。
最近はスマホで動画を見せることもあると思いますが、「まだスマホは早いかな」と考える方には特におすすめ。コンパクトなサイズもあり、持ち運びに便利なのも嬉しいポイントです。
また、子どもが自分で楽しめるのも魅力です。
家事の合間やちょっとした空き時間に、やけに静かだなと思ったら、ウォーリー探しに没頭していることが何度もありました。
そして、時間が経つと見つけたはずのウォーリーの場所を忘れてしまう!という特性のおかげで、
何度でも新鮮な気持ちで楽しめます。私だけかもしれませんが。笑
懐かしさと新しい発見を同時に味わえる、まさに世代を超えて愛される絵本ですね!
さて、ここからご紹介する4冊の絵本は、私が大人になってから出会った絵本たちです。
子供が親になった時、子供時代を懐かしく思いながら読んでもらえたらうれしいなと思います。
バムとケロのにちようび 島田ゆか(1994年)
『バムとケロ』シリーズは個性豊かなキャラクターの日常がかわいすぎておもしろすぎて、子供と一緒に全作を通して大ファンになった絵本です。


主人公の犬「バム」は穏やかで面倒見がよく、カエルの「ケロ」は好奇心旺盛でやんちゃ。
性格が全く異なる2人のやり取りがコミカルで、気づいたら自然と笑顔になっています。
最初はなんだか個性的な絵の絵本だなぁくらいに思っていたのですが、読んでみるとその魅力にどんどんハマっていく・・・本当に不思議な魅力を持つ絵本です。
雨の降るなんでもない日曜日が、バムとケロちゃんの全力投球な姿勢によって、楽しくてワクワクして、いろんな意味でも忘れられない特別な一日になります。
ケロちゃんの3歳児のようなイタズラと、次々と繰り出す右斜め上をいくハプニングに対し、バムは寛容さと愛情で接していて、本当に見習いたいくらいです。笑
バムケロシリーズを通じて登場する他のキャラクターも個性的でかわいいですし、サブキャラクターの小さな生き物たちもたくさんいて、探し絵のようで、大人も一緒になって楽しめるポイントです。
おふとんさん コンドウアキ(2017年)
リラックマの生みの親、コンドウアキさんによるとにかく癒されまくる絵本です。


『おふとんさん』はどんな時でも暖かくふんわりと寄り添ってくれて、不安な気持ちをそのおふとんで優しく包み込んでくれて、とにかく幸せな気持ちになります。
絵本『おふとんさん』は、作者のコンドウアキさんが自身の「眠りたい」という願望と、夜なかなか寝付けない人々の気持ちが一致したことから生まれた作品なんだそうです。
私は眠ることも好きですし、おふとんの中のぬくぬくした空間も大好きですが、絵本を読んでいると、小さい頃に親戚の家で感じたような子供だけ先に寝かされる、ちょっとした不安のような気持ちを思い出しました。
『おふとんさん』シリーズでは、寝たくないこども、眠れないこども、朝起きられないこどものお話があって、子育て中の親御さんには助かるツールですね!
『おふとんさん』の温かさに包まれて幸せないっぱいの気持ちになれますよ♡
パンどろぼう 柴田ケイコ(2020年)
ジャジャーン!みんな大好き『パンどろぼう』の登場です。
主人公の『パンどろぼう』がとにかく魅力的。
どろぼうなんですが、素直で真面目で一生懸命。そしてパンへの愛とパン職人の腕はピカイチ!
そんな『パンどろぼう』が繰り広げるハプニング、いや大冒険に目が離せません。
多くの日本人を虜♡にしているキャラクターではないでしょうか。
パンを被った『パンどろぼう』がパンを盗んでパン屋さんに注意してパンを焼いて・・・
シュールな展開に子供が大笑いし、それにつられて大人も大笑い。
子供とお母さんが笑っている家庭は幸せに満ち溢れていること間違いなしです。
新しいシリーズが出ると話題になる作品ですが、まずはシリーズ1作目の『パンどろぼう』からお読みいただき、続いてシリーズ4作品目となる『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』をお勧めします。
『パンどろぼう』がどのようにパンどろぼうに変貌を遂げていったのか、秘密のベールに包まれていた『パンどろぼう』の過去を知ることができるでしょう。笑
ぜひ家内安全、世界平和のためにもご家庭に一冊『パンどろぼう』をお勧めします。
あんなに あんなに ヨシタケシンスケ(2021年)
絵本『あんなにあんなに』は、時間の経過とともに、子どもの成長と親の思いが丁寧に描かれ、日々の忙しさの中で忘れがちな「今この瞬間の大切さ」を思い出させてくれる作品として、多くの人々に支持されています。
『あんなにあんなに』というフレーズに沿って、
「あんなに泣いてたのに もうこんな」
「あんなに小さかったのに もうこんな」と、子供の成長を追っていきます。
ヨシタケシンスケさんの愛らしいイラストに、我が子の愛おしい瞬間を重ねて自然と目尻が下がり、胸に幸せな気持ちがじんわり広がります。そして、今この瞬間もあっという間に過去の出来事になるのだと、はっとされます。
物語の前半部分は小さな子供時代を振り返っているのですが、途中からお母さんが若かった頃に視点が変わっていたり、ユーモアたっぷりで本当におもしろいです。
スリムなお母さんがぽっちゃりになっているのを見て、「これお母さんの将来?」とうちの子供は私をいじってきます。笑
子育て中のお母さんはもちろん、子育てがひと段落したお母さん、そしておばあちゃんにも共感できるところばかりです!
人気絵本雑誌MOEの「第14回MOE絵本屋さん大賞2021」で第1位を受賞しています。
これから世代を超えてずっと読み続けられる絵本になることは間違いないでしょう!
まとめ
今日は【世代を超えて愛される絵本】をテーマに紹介しました。
世代を超えて愛される絵本は、シンプルながら深みのあるストーリー、美しいイラスト、普遍的なテーマを持ち、読む人の心に残る作品です。それらの絵本を通じて、子どもは言葉や感受性を育み、大人は改めて人生の大切なことを思い出すことができます。
あなたにとって、思い出深い絵本はありますか?
紹介した絵本をもう一度チェックしたい方はこちら
スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし (レオ=レオニシリーズ 1) [ レオ・レオニ ]
ボードブック はらぺこあおむし (偕成社・ボードブック) [ エリック・カール ]
NEWウォーリーをさがせ! [ マーティン・ハンドフォード ]
バムとケロのにちようび (バムとケロのなかまたち) [ 島田 ゆか ]
パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち [ 柴田 ケイコ ]
あんなに あんなに (一般書 337) [ ヨシタケ シンスケ ]
🦉フクさんのブログでは、絵本を読んだ感想や気づき、日常で見つけたワクワクすることなどを書いています。日々の生活に安らぎや癒しを、そして時には刺激をプレゼントできたらいいなと思います。
“お気に入りの絵本”を見つける参考になれば、とても嬉しいです。

ほーっとひと息。今日も素晴らしい1日でありますように🌿
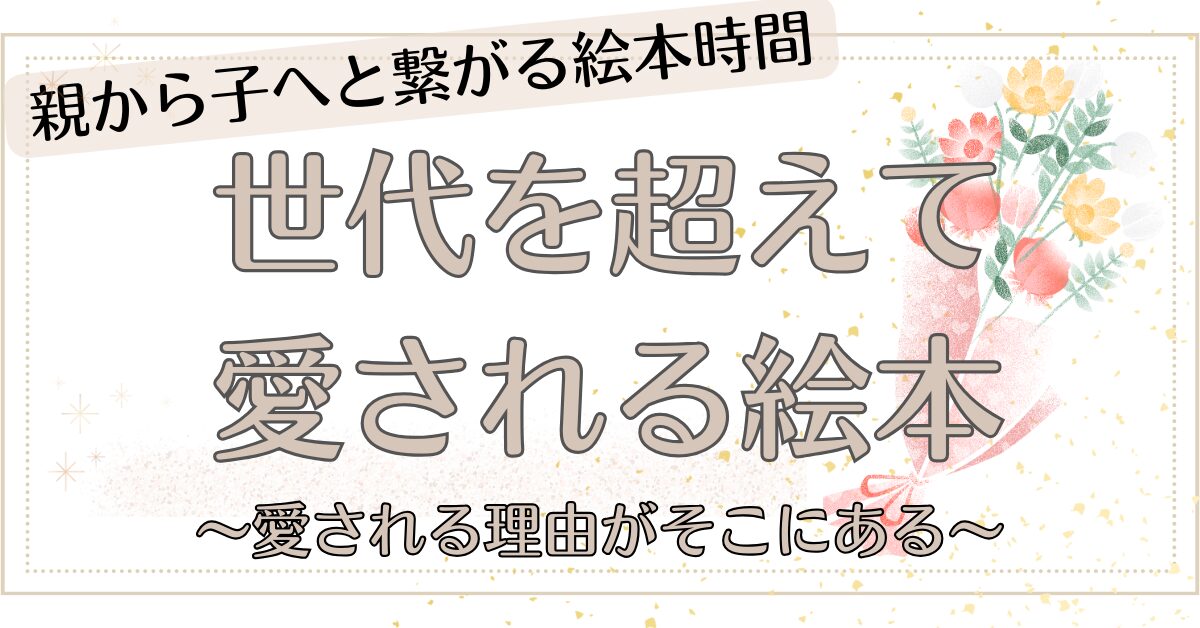















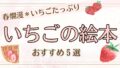
コメント